こんにちは、こみです。
今回は、元保育士・そして母としての視点から、
「これからの教育に必要な力」についてお話しします。
AIやSNSが当たり前になった今、
「子どもにどんな力をつけてあげればいいのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
私自身、保育現場や子育てを通して「このままでいいのかな?」と何度も考えてきました。
そこでこの記事では、
- これからの教育に必要だと感じる5つの力
- 子どもの未来を育てるために、家庭でできること
について、具体的にお伝えしていきます。
教育は“誰か”に任せるものじゃない

「教育は学校で学ぶもの」
「親はサポートでいい」
そんなふうに思っていた時期もありました。
でも、保育士として子どもたちと関わり、
母として日々の育児に向き合う中で気づいたのは、
教育は、家庭や地域、そして“社会の空気”も含めて、みんなでつくっていくものだということです。
それを前提に、私が大切だと感じている「これからの教育に必要な5つの力」をご紹介します。
1. 正解のない問いに向き合う力
これからの時代は、ひとつの正解だけを探す力よりも、
「自分で問いを立てて、考え続ける力」が求められていくと思います。
例えば保育の現場でも、
子どもたちは「なんで?」「どうして?」とたくさんの問いを投げかけてきます。
大人がすぐに答えを出すのではなく、
「一緒に考えてみようか」と関わることで、考える力や柔軟性が育ちます。
2. 自己理解と自己表現の力
自分が何を感じているのか、何を大切にしたいのか。
それを言葉にしたり、絵や音で表現したりできることも、これからの時代には欠かせない力です。
私自身、お絵かきムービーという仕事を始めてから、
「自分の思いを表現する」ことの大切さを改めて実感しました。
完璧な表現じゃなくてもいい。
「こう思ってるんだよ」と伝える力は、生きる力に直結します。
3. デジタルとの付き合い方と創造力

タブレットやスマホ、AI。
子どもたちはどんどんデジタルツールに触れる時代に生きています。
大切なのは、それらを“使いこなす”力と、
「何をどう創るか」を考える力のバランス。
動画を“見る側”だけでなく、
「自分でつくってみたい」と思う気持ちを大事にできるといいなと思います。
4. 多様性を受け入れる力
これからの社会では、価値観や背景の違う人と一緒に生きていく力が必要になります。
「そんな考え方もあるんだね」
「そう思ったんだね」
子どもの発言に対して、否定ではなく共感や問い返しを重ねることで、
他者への理解力が自然と育っていきます。
5. 学び続ける姿勢(好奇心)
最後に伝えたいのは、「学び続ける姿勢」そのものです。
正直、大人の私たちだってわからないことはたくさんありますよね。
でもそれでいいんです。
「わからないから一緒に調べてみよう」
「ママも初めて知ったよ!」
そんなふうに、学びを一緒に楽しめる関係が、子どもの好奇心や意欲につながっていきます。
家庭でできる関わり方|今日からできるヒント

「じゃあ、家庭では何ができるの?」と迷う方に向けて、
日々の生活の中で取り入れやすい工夫をご紹介します。
● 子どもの「なんで?」にすぐ答えない
→「どう思う?」「一緒に調べてみよう」と返してみる
● 表現の場を用意する
→ 絵や工作、日記など、言葉以外のアウトプットも◎
● 自分の価値観を押しつけない
→ 「そういう考え方もあるよね」と多様性を受け入れる姿勢を見せる
● 大人も学ぶ姿を見せる
→ 新しいことに挑戦する姿を子どもに見せるのも立派な教育!
まとめ|子どもと一緒に“考え続ける力”を育てよう
教育は、決して特別なものではありません。
日々の何気ない会話や関わりの中に、“学びのタネ”はたくさんあります。
私たち大人が、子どもと一緒に考え続けることで、
子どもたちは未来を生き抜く力を自然と身につけていくはずです。
ぜひ、今日からの関わりの中で意識してみてくださいね。
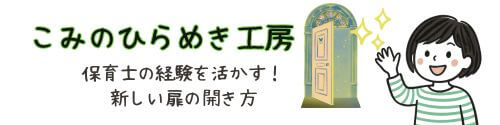
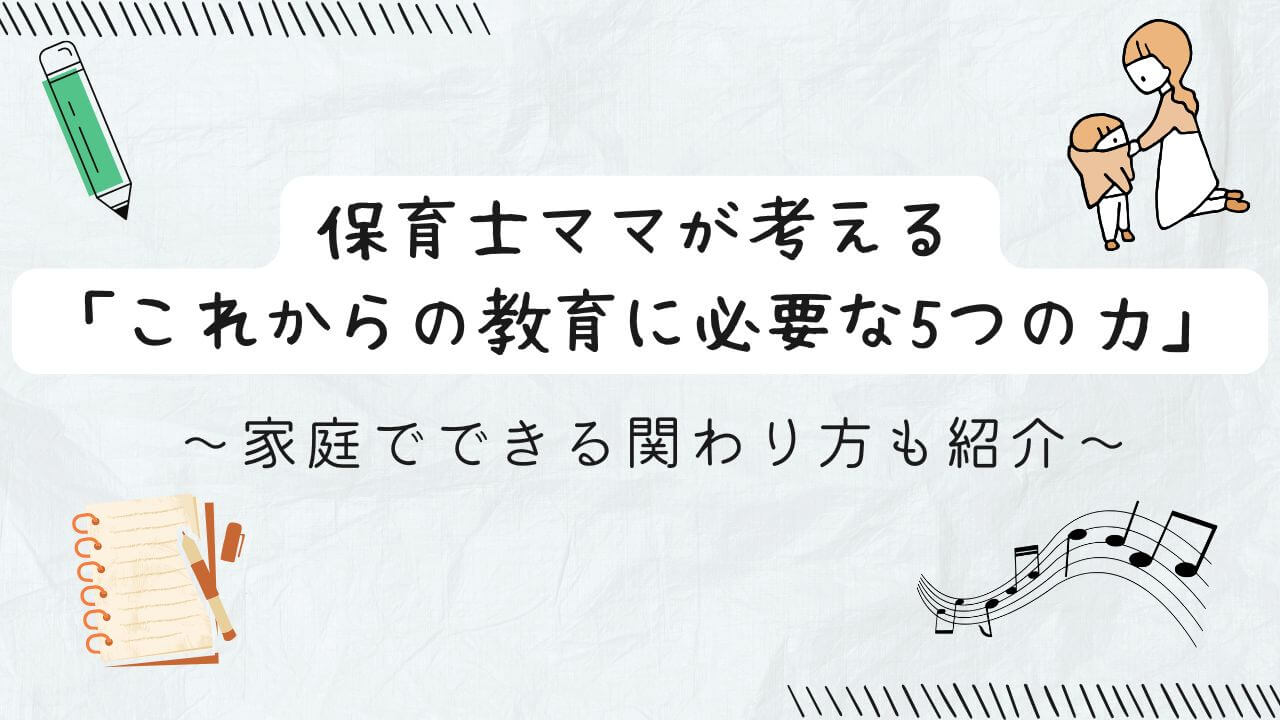


コメント